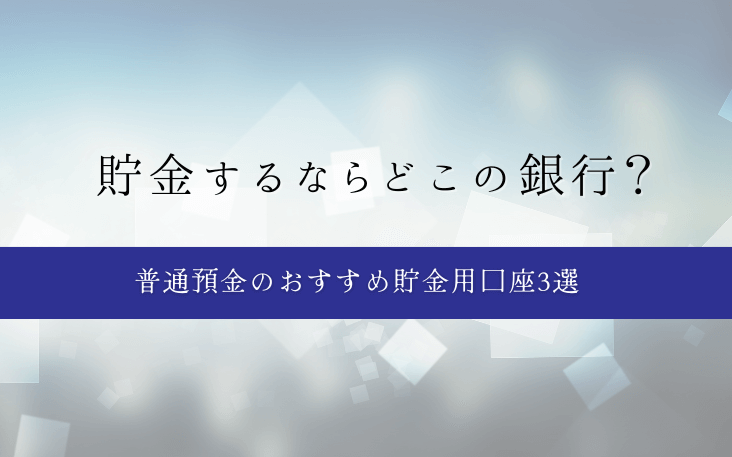贈与税とは?基礎知識からかからない方法までわかりやすく解説

目次
「親から近々まとまった額の贈与を受けるのだけど、贈与税はかかるのだろうか?」
「できれば税金は抑えたいけど、何か方法はないのかな……」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。両親からの贈与は資産形成の大きなチャンスです。ただし、贈与税を適切に把握しておかないと、思わぬ税負担に直面するかもしれません。
そこで本記事では、贈与税の基礎知識から税金を抑える具体的な方法まで、わかりやすく解説します。正しい知識を身につけることで、将来の資産形成に向けて贈与を有効活用できるようになるはずです。
- 贈与税の基本的な仕組みと計算方法
- 贈与税がかからない6つの方法
- 贈与を受ける際の注意点
- 大きな贈与を受ける予定がある人
- 贈与を受けたが贈与税がかかるか知りたい人
- 贈与税が掛からない方法を知りたい人
贈与税とは?誰が払う?

「贈与税」は多くの人にとって、あまり身近な税金ではないことでしょう。まずは贈与税の基礎知識を身につけられるよう、わかりやすく解説していきます。
贈与税とは
贈与税とは、個人間で財産を移転した際に納める税金です。相続税の補完税として位置づけられており、相続税逃れを防ぐ目的で設けられています。
対象となるのは現金や預貯金といった金銭だけでなく、株式等の有価証券、自動車や家財道具、貴金属なども含まれます。
尚、生活費や教育費などを通常必要と認められる額だけ都度贈与する際は、贈与税の対象にはなりません。
贈与税を払うのは「受贈者」
贈与税を納めるのは「贈与を受けた人(受贈者)」です。その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額に基づいて計算します。
例えば、同じ年に 父から300万円、母から200万円の贈与を受けた場合、500万円が贈与税の計算対象となります。
確定申告時に納付
贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに確定申告を行い、納付しなければなりません。
納付方法は所轄税務署や金融機関の窓口での現金納付のほか、インターネットバンキングやクレジットカードでの納付など、キャッシュレス決済にも対応しています。
贈与税は金銭で一度に納付するのが原則です。しかしすぐに準備するのが難しい場合は、一定の条件を満たせば延納できる取り扱いもあります。
贈与税はいくらから必要?
贈与税には「基礎控除」という誰もが使える免税枠が設定されています。この枠を超えない額の贈与には、贈与税はかかりません。
ここでは贈与の2つの方法における基礎控除を中心に、贈与額がいくらになると税金が必要となるか解説していきます。
基礎控除110万円までは非課税
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。110万円以内の贈与であれば贈与税は発生せず、 確定申告も不要です。
ただし、基礎控除を利用した贈与であっても、将来相続が発生した際に相続財産に加算される可能性があります。これを「持ち戻し」と言いますが、2023年度税制改正により持ち戻しの期間が相続発生前3年から7年まで延長され、実質的な増税となりました。
そのため、将来の相続も踏まえた対策が必要です。基礎控除内の贈与であっても贈与契約書を作っておくなど、贈与したことを記録しておくことをおすすめします。
相続時精算課税制度を使えば2,610万円まで非課税に
相続時精算課税制度を利用すると、基礎控除110万円にくわえ特別控除2,500万円が適用され、最大2,610万円まで贈与税が非課税となります。
この制度を使えば贈与税の非課税枠は大きくなりますが、これは贈与した財産が相続発生時に相続税の課税対象となるからです。
本制度を使うには税務署へ書類の提出が必要となります。また、贈与者・受贈者ともに年齢の制限がある点にも注意しましょう。
贈与税の税率は?【親子間の贈与は低くなる】
贈与税の税率は、親など直系尊属からの贈与かそれ以外かにより異なります。
ここでは2種類の贈与税率について紹介します。基礎控除を超えてしまったら贈与税はいくらかかるのか、具体的にみていきましょう。
特例贈与の贈与税率
直系尊属(父母や祖父母)から20歳以上の子や孫への贈与は、特例税率が適用されます。具体的な税率は以下の通りです。
| 区分 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
例えば、父から600万円の贈与を受けた場合は次の通り計算します。
※各種特例は考慮しない。
- 基礎控除110万円を差し引いた490万円が課税対象
- 490万円×20%-30万円=68万円
このケースでは68万円を贈与税として納めなければなりません。かなり大きな額が課税されることがわかるでしょう。
一般贈与の贈与税率
特例贈与に該当しない場合(例:叔父からの贈与)は、以下の一般税率が適用されます。
| 区分 | 税率 | 税率 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
例えば、叔父から600万円の贈与を受けた場合、次のような計算となります。
- 基礎控除110万円を差し引いた490万円が課税対象
- 490万円×30%-65万円=82万円
同じ金額の贈与であっても、誰から受けるかによって税金が大きく異なるのです。
相続時精算課税制度選択時の税率
相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除110万円と特別控除2,500万円の合計2,610万円を超えた部分に対し、一律20%の税率が適用されます。
将来の相続を見据えて生前贈与を行う場合、この制度が有利になるケースもあります。資産をトータルに見たうえで、本制度を選ぶか検討しましょう。
贈与税がかからない方法6選

高い税率の贈与税、できるだけ抑えたいという人へ。ここでは贈与税をかからなくするために次の6つの方法をご紹介します。
- 基礎控除内で毎年贈与する
- 相続時精算課税制度を選択する
- 住宅取得等資金として贈与する
- 教育資金として孫に贈与する
- 結婚・子育て資金として子どもに贈与する
- 居住用不動産の贈与にかかる配偶者控除を活用する
贈与税には様々な特例制度があり、これらを活用することで税負担を大幅に軽減できます。ご自身で使える特例はないか、次から詳しく確認していきましょう。
基礎控除内で毎年贈与する
基礎控除を活用し毎年110万円以内の贈与を複数年に分けて行う方法で、「暦年贈与」と言います。
基礎控除以内の贈与ですので、申告の必要もなく手軽に行える方法です。しかし先述したとおり、相続発生時に生前に行った贈与財産が、相続財産とみなされる可能性がある点には気を付けましょう。
また「定期贈与」とみなされないために、次のような対策が必要です。
- 贈与の時期を分散させる
- 贈与する金額を変える
- 贈与契約書を毎回作成する
- 資金移動の記録を残す
| 定期贈与とは 「毎年100万円を10年間贈与する」というように、あらかじめ贈与する金額や期間を約束しておくことです。このケースなら「100万円×10年=1000万円」の贈与契約が結ばれたことになり、1000万円が贈与税の課税対象となります。 |
暦年贈与は簡単にできる方法ではありますが、デメリットやリスクも理解した上で実践するようにしましょう。
相続時精算課税制度を選択する
相続時精算課税制度を選べば、贈与した財産が将来の相続財産に加算されることを前提に、2,610万円まで贈与税を非課税にできます。まとまった資金の贈与をする人に有効な制度です。
適用するには、次の年齢の制限がある点に注意が必要です。
- 贈与者の年齢が60歳以上(贈与の年の1月1日時点)
- 受贈者の年齢が18歳以上(贈与の年の1月1日時点)
また、本制度は一度選択すると取り消しができないというデメリットもあります。制度を適用するかどうか、贈与する財産額を鑑みて慎重に判断しましょう。
住宅取得等資金として贈与する
住宅を新築・取得したり、増改築したりするために贈与を行った場合、贈与資金に対し次の金額が非課税となります。「子どもが近々住宅を購入する」といった話がある人は、ぜひ活用したい制度です。
本特例の非課税枠は以下の通りです。
- 一般住宅:最大500万円まで
- 省エネ住宅:最大1,000万円まで
※省エネ住宅に該当するための基準は国税庁ホームページをご確認ください。
尚、この特例を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
- 直系尊属からの贈与であること
- 受贈者が18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)
- 受贈者の年収が2,000万円未満
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住開始
- その後も継続して居住する予定であること
他にも条件が定められていますので、こちらも詳しくは国税庁ホームページで確認するようにしましょう。
教育資金として孫に贈与する
祖父母から孫への教育資金贈与という目的があれば、最大1,500万円までが非課税で贈与できます。
たとえば、大学進学費用や留学費用などまとまった教育資金を準備したい場合に有効ですし、まとめて贈与しておき、将来の教育費として少しずつ使っていくことも可能です。
本制度には次の適用条件があります。
- 受贈者の年齢が30歳未満
- 受贈者の合計所得金額が1,000万円未満
- 直系尊属(祖父母など)からの贈与
学校の授業料や入学金はもちろん、習い事や塾の費用なども対象となりますが、学校教育以外の費用は500万円までが非課税の限度となります。教育費とみなされる資金の詳細は、文部科学省ホームページをご確認ください。
この制度を利用するには金融機関で「教育資金贈与専用口座」を開設する必要があり、手続きも少々煩雑です。
また、契約終了時(受贈者が30歳に達したとき等)に残額があれば贈与税が、贈与者死亡時には相続税が課される可能性がある点にも注意しましょう。
結婚・子育て資金として子どもに贈与する
結婚や子育てにかかる資金の贈与については、1,000万円までが非課税となる特例があります。
対象となるのは、挙式費用や転居費用といった結婚費用、不妊治療や分娩費など出産費用のほか、保育料など乳幼児の子育てに必要な費用も対象となります。詳しくはこども家庭庁のホームページをご確認ください。
本制度の適用には、次の条件があります。
- 受贈者が18歳以上50歳未満
- 受贈者の合計所得金額が1,000万円未満
- 直系尊属(祖父母や父母)などからの贈与
教育資金の贈与の特例と同様、本特例も専用口座の開設が必要なことや、受贈者が50歳到達時の残高に贈与税がかかること、贈与者の死亡時に相続税がかかる可能性があることに注意しましょう。
居住用不動産の贈与にかかる配偶者控除を活用する
夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、最大2,000万円までの配偶者控除が適用される制度があります。これは一般に「おしどり贈与」と呼ばれています。
適用できる条件は以下の通りです。
- 婚姻期間が20年以上
- 贈与後の居住要件あり
このほか、不動産の贈与には登録免許税や不動産取得税がかかることも知っておきましょう。相続で取得する場合にはこれらの税金に対し軽減措置がありますが、贈与の場合はありません。贈与税はかからなくとも、思わぬ税金がかかってしまう可能性があります。
本制度の利用にあたっては、将来の相続を見据えたうえで慎重に検討することをおすすめします。
まとめ|贈与税とは何かを理解し正しい対策を
贈与税について理解を深め、各種特例制度を活用することで、より効果的な資産移転が可能となります。
基本となるのは年間110万円の基礎控除ですが、親から子への贈与は税率が優遇されています。さらに目的に応じた様々な特例制度を組み合わせることで、より大きな非課税枠を得られる可能性も秘めているのです。
ただし、これらの制度はそれぞれ細かい要件があり、手続きも複雑です。利用を検討する際は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
自身の状況に最適な贈与の方法を選ぶことで、将来の資産形成に大いに役立てましょう。
贈与税に関するよくある質問
Q.贈与税を納付し忘れたらどうなりますか?
A.延滞税や加算税が課されます。
延滞税は2か月経過後には年8.7%の割合で課され、納付が遅れるにつれ大きな金額に膨れ上がってしまいます。
納付困難な場合は延納制度もありますので、条件を満たせるかどうか知りたい人は国税庁ホームページを確認してみてください。
Q.親から100万円の贈与を受けたら贈与税はかかりますか?
A.基礎控除110万円以内であれば贈与税はかかりません。申告も不要です。
ただし、贈与税は贈与を受けた人がもらった金額をもとに計算しますので、同じ年に他の贈与を受けていないか確認しましょう。
Q.贈与税の申告漏れはばれますか?
A.相続時の調査や大口の資金異動がきっかけでばれるリスクは大いにあります。近年マイナンバー制度が始まったことにより、いずれ国により所得把握がされるようになれば、さらに申告漏れは発覚しやすくなるでしょう。
申告漏れが発覚した場合、悪質な脱税とみなされると重加算税(本来の税額の35%~50%)が課される可能性もあります。適切な申告と納税を心がけましょう。